着物と呉服は日本の伝統文化に深く根ざした存在ですが、両者が混同されるようになった時期については様々な説があります。この記事では、江戸時代を中心に、着物と呉服の違い、そしてその混同が始まった背景について考察します。
1. 着物と呉服の定義
着物は日本の伝統的な衣装であり、長い歴史を有しています。呉服は、中国の呉という国から伝わった絹の生地を指します。呉服という言葉は、元々は絹の生地を指していましたが、後に日本では絹の生地を使った着物全般を指すようになりました。したがって、呉服と着物はその本来の意味において異なるものです。
2. 江戸時代における呉服屋の役割
江戸時代、呉服屋は主に絹の生地を販売していました。着物の仕立ては購入者自身が行うことが多く、仕立て職人に依頼するか、自ら縫製していました。そのため、呉服屋は生地を提供するだけで、完成した着物を売ることは少なかったとされています。
3. 近代化とともに起こった混同
明治時代以降、西洋化が進み、洋服が流行し始めました。この時期に、呉服屋は着物の仕立てを手掛けるようになり、販売も行うようになりました。洋服の普及に対抗する形で、呉服屋は着物を仕立てるサービスを提供し、着物と呉服が混同されるようになったとされています。
4. 現代における呉服と着物の混同
今日では、呉服という言葉は着物の絹の生地を指すことが多く、着物そのものと混同されがちです。特に若い世代においては、呉服という言葉が「着物」を指す場合が多く見受けられます。しかし、伝統的には、呉服はあくまで生地に関する言葉であり、着物とは厳密には異なります。
5. まとめ
着物と呉服の混同が始まった時期は、江戸時代末期から明治時代にかけての西洋化と洋服の流行の中であったと考えられます。呉服屋が着物を仕立てるようになり、庶民の間で呉服=着物という認識が広がったことがその背景にあります。これにより、今日では呉服と着物が混同されることが多いですが、両者には歴史的な違いがあることを理解しておくことが大切です。
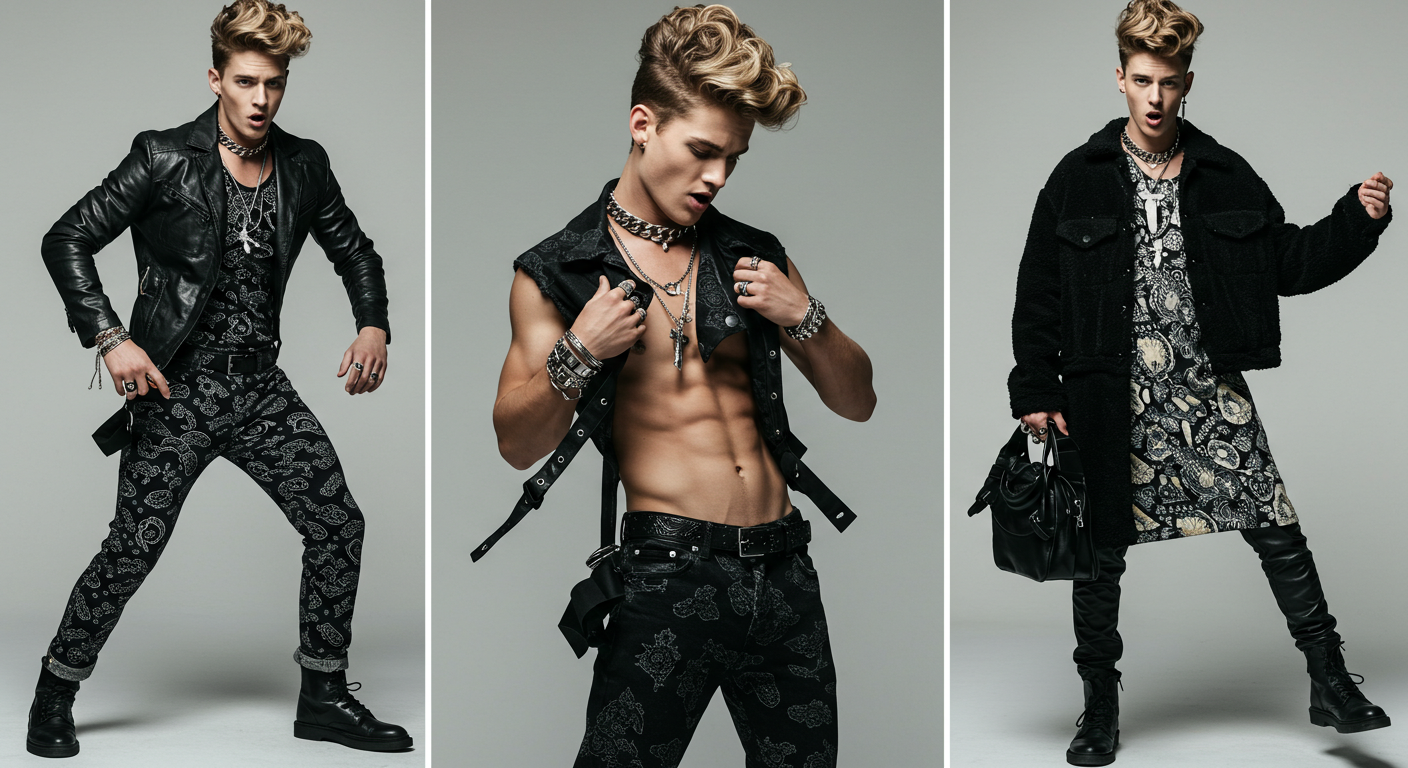


コメント