夏目漱石の『それから』に登場する三千代の浴衣と、明治後期の暑さについての描写に関する疑問を解決するための記事です。本文では、三千代が登場する場面を元に、当時の日本の気温や浴衣の質素なデザインについて解説します。
1. 明治後期の暑さとその気温
三千代が「此暑(このあつさ)を冒して前日の約を履んだ」とある描写は、当時の暑さの厳しさを示しています。明治後期、特に夏季の日本では、気温が30度を超えることが一般的でした。都市部では、気温が35度を超えることもあり、特に暑い夏の時期では、日中の外出はかなり過酷だったと考えられます。これを踏まえると、三千代が暑さを冒して約束を守りに出かける姿は、当時の人々の生活様式をよく反映しています。
2. 三千代の浴衣の素材と柄
「質素な白地の浴衣」の描写にある「白地」という表現から、三千代の浴衣はシンプルでありながらも涼しげな印象を与えます。当時の女性用浴衣は、一般的に麻や綿などの通気性の良い素材で作られており、夏の暑さに対応できるように工夫されていました。柄については、白地の浴衣に小さな花柄や模様が刺繍されていた可能性が高いです。この時期、浴衣は派手な柄ではなく、控えめなデザインが多かったとされています。
3. 風呂敷包みと手帕の使用
三千代が「手帛を出し掛けた所であつた」という描写から、当時の女性が日常的に手帕を持ち歩いていたことが伺えます。手帕は、暑さをしのぐために顔や首を拭いたり、身の回りの清潔さを保つために使用されました。また、風呂敷包みを抱えている描写も、当時の女性が大切な物を風呂敷で包んで持ち運んでいた習慣を反映しています。これらの描写は、当時の女性の日常生活を垣間見ることができる貴重な情報です。
4. まとめ
『それから』に登場する三千代の浴衣や暑さの描写は、明治後期の生活環境や文化を理解する上で非常に重要です。暑さの厳しい夏に、シンプルで涼しげな白地の浴衣を着る三千代の姿は、当時の日本の美意識や女性の日常生活を反映しています。また、浴衣の素材や柄、日常生活の中での風呂敷や手帕の使用は、当時の日本人の生活感を伝えてくれる貴重な資料です。
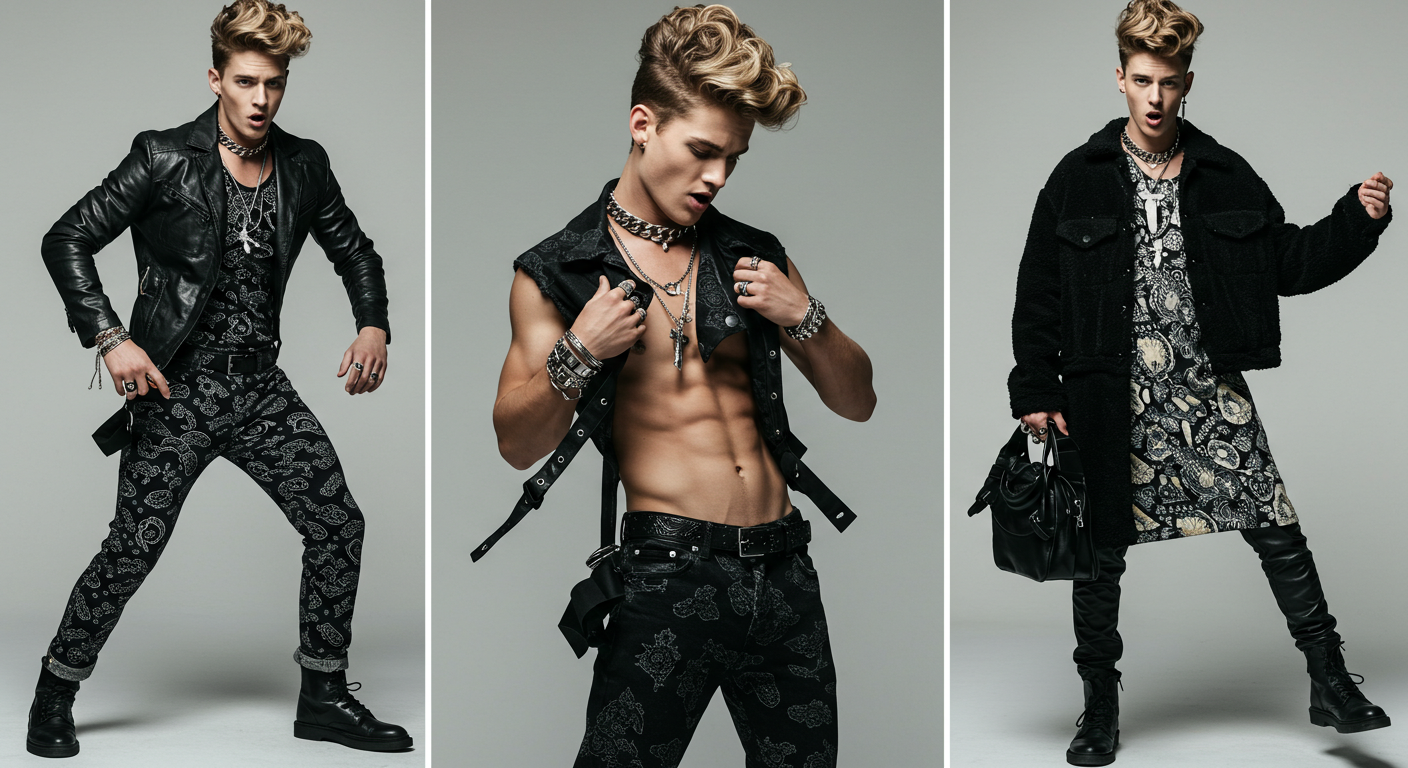


コメント